3世紀の日中関係
晋の陳寿が編纂した「三国志」『魏書』東夷伝倭人条(とういでんわじんのじょう)(魏志倭人伝)によると、約30の小国の連合体が倭に存在し、中国に朝貢を行っていた。ちなみに三国とは魏呉蜀のことである。
邪馬台国
倭で約30カ国の盟主となった国は邪馬台国。
場所については畿内説と北九州説でもめている。
ちなみに北九州説は主に東大閥、
畿内説は主に京大閥が提唱している。
奈良県桜井市の纒向遺跡は近畿説の重要な根拠となっている。
また、奈良県の黒塚古墳から出た三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)が畿内説を補強。
史料
倭人は帯方の東南大海にあり、山島に依りて国邑をなす。旧百余国、漢の時朝見する者あり、今使訳通ずるところ三十国。(帯方)郡より倭に至るには・・・(狗邪韓国→対馬国→一支(いき)国→末盧(まつら)国→伊都国→不弥国→投馬国)・・・邪馬台国に至る。女王の都する所なり。
女王国より以北には一大率を置き、諸国を検察せしむ。
下戸・大人(だいじん)と道路に相逢えば、逡巡して草に入り、辞を伝へ事を説くには、或いは蹲り(うずくまり)、或いは跪き、両手は地に拠り之が恭敬を為す。
その国、本亦男子を以って王と為す。住(とど)まること七、八十年。倭国乱れそ、相攻伐して年を歴たり。乃ち共に一女子を立てて王と為す。名付けて卑弥呼(姫巫女・ひみこ)という。鬼道を事とし、能く衆を惑はす。年すでに長大なるも夫壻(ふせい)無し。男弟有り、佐けて国を治む。
景初二年六月、倭の女王、大夫難升米(なしめ)らを遣わし、都に詣(いた)り、天子に詣りて朝献せんことを求む。
卑弥呼以って死す。大いに冢(つか)を作る。径百余国、徇葬(じゅんそう)する者、奴婢百余人。更に男王立てしも、国中服せず。更々(こもごも)相誅殺し、当時千余人を殺す。復た卑弥呼の宗女壹与(いよ)の年十三なるを立てて王と為す。国中遂に定まる。魏志倭人伝
史料の注意
- 景初二年は魏志倭人伝の原稿ミス。正しくは三年。西暦でいうと239年。
- 帯方郡は遼東に勢力を置く公孫氏が楽浪郡の南部を分割して設置したもの。今のソウルあたり。
- 鬼道・・・巫女的呪術
- 卑弥呼は難升米と呼ばれる大夫を派遣。
- 大人と下戸は身分階級のこと。
- 壹与が卑弥呼の事実上次の後継者。
- 上にはないが、倭国の中には市もあり、大倭と呼ばれる役人が管轄した。
- 壹与の使者派遣は266年。
- ちなみに一支国の中心集落と考えられているのは長崎県、原の辻遺跡。
邪馬台国と拘奴国
卑弥呼は239年魏に使いを派遣して、親魏倭王の称号を得た。これで拘奴国との抗争を有利にしようとした。このときに金印紫綬や銅鏡もいただいた。拘奴国の国王は卑弥弓呼(ひみここ)。
邪馬台国でわかっていること
邪馬台国の卑弥呼(姫巫女とも卑弥呼は中国人による蔑称という説もある)は、伊都国に一大率と呼ばれる監督官を駐在させ、各国に地方官を王の目・王の耳のように派遣しました。
卑弥呼に関しては、
「鬼道につかえ、よく衆を惑はす」
魏志倭人伝
にかかれていますね。しかも、イメージとは違い、
卑弥呼は高齢のおばあさんだ!
と書いています。
そのことから、
卑弥呼は呪術的・宗教的な支配者としての彩りが強く、
シャーマンだったと考えられています。
親魏倭王・卑弥呼
卑弥呼は239年に、
卑弥呼は部下である難升米(なしめ)を帯方郡(現在の朝鮮半島北部一帯)を経て、
北魏に派遣しました。
魏からは、
親魏倭王の称号と、
金印紫綬を得ました。
錦や絹、金、銅などが授けられました。
卑弥呼の生活
卑弥呼は倭の数十の小国からの共同代表という形で、
選ばれた巫女です。
卑弥呼には夫がおらず、
弟がいて、弟が政治を行っていました。
大勢の奴隷を従えて、
宮殿の奥深くに住んでいました。
その弟という男一人を除いて、
ほとんど人とはふれあいませんでした。
卑弥呼の死と倭国大乱
狗奴国との戦争中に卑弥呼はなくなりました。
径は100歩ほどの墳墓が見つかり、
奴婢・100名あまりが殺されて一緒に葬られました。
卑弥呼の死後、男の王が代表になったが、
国はおさまらず、卑弥呼の宗女・壱与を立てて女王になり、
戦乱がしずまりました。
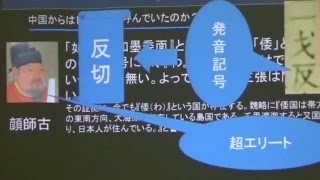


コメント