前回のあらすじ

「和泉に『堺公方府』が成立」 足利義維が阿波から上陸
...
中嶋の戦いの背景
堺公方府の河内国守護・畠山義宣
(はたけやまよしのぶ/義尭(よしあき)、義英(よしひで)の子)と
河内守護代・木沢長政(きざわながまさ)
の対立が原因です。
1531年8月に、
畠山義宣が木沢長政の飯盛城(いいもりじょう)を攻めたことが戦いのきっかけとなりました。
彼らの協力者
畠山義宣への協力者
畠山義宣に協力したのが三好元長と一族の三好勝宗(みよしかつむね)です。
木沢長政への協力者
木沢長政を助けたのは幕府の管領・細川晴元です。
中嶋の戦い
8月20日に起きた
摂津国・中嶋で行われた戦い(中嶋の戦い)では
木沢長政が畠山義宣軍を撃退しました。
そして1532年5月19日、
畠山義宣方は再び木沢長政への攻撃を行いました。
木沢長政らの諫言を受け入れ、
三好勝宗が三好一族であるため、
三好元長打倒を決意した晴元は本願寺証如に協力を求めます。
細川晴元・本願寺の連合
6月5日に本願寺証如(ほんがんじしょうにょ)は山科をたって、
摂津・石山本願寺に向かいました。
本願寺証如の命で蜂起した
摂津・河内・和泉の門徒勢が動員して飯盛山城を攻め、
6月17日には畠山義宣は自刃を遂げました。
さらには三好元長を攻め、
戦いは門徒勢と細川軍が勝利し、
敗北した三好元長は願本寺で自刃しました。
足利義維の失脚
三好元長と同じ願本寺にいた足利義維も自害を図ったものの、
晴元におしとどめられます。
後に淡路へ去り、名前を「足利義冬」と改めます。
翌年には阿波平島荘(徳島県阿南市那賀川町)に移り、
ここは阿波公方・平島公方と呼ばれました。
堺公方府の崩壊へ
この元長の死と足利義維の失脚で堺公方府は崩壊しましたが、8月4日に本願寺門徒が晴元・長政を攻撃するという新たな展開をみせます。





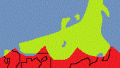
コメント