前回、

後三条天皇による「延久の荘園整理令」
藤原道長の子、藤原頼通と藤原教通には子どもができませんでした。そんな中、藤原氏と血縁関係が薄い後三条天皇が即位します。後三条天皇は藤原氏の荘園を減らし、藤原氏の勢力を減らすために、荘園整理令を出します。藤原氏の摂関政治は力を失っていきます。
の続きです。
武士団
つわもの(兵)
都では、武力で朝廷に仕える人々があらわれました。
地方でも、有力農民や地元の公の職に勤める
在庁官人と呼ばれる人々のなかに、
武装するものもあらわれてきました。
こうした人々を兵(つわもの)とよびます。
武士団
兵のリーダーが棟梁(とうりょう)です。
家子(いえのこ)とよばれる一族、
郎党(ろうとう)とよばれる従者を率いて、
武士団を形成しました。
武士団の特徴
東国
東国は馬の産地でした。
そういう訳あって、弓馬が上手な武士が多かったのです。
西国
瀬戸内海のような海がある関係上、
船団を組んだ武士、つまり、海賊が多かったのです。
二大棟梁
各地にできた小さな武士団は、
やがて大きな武士団へと統合されていきます。
その大きな武士団の棟梁とされたのが、
平氏と源氏なのです。
平氏と源氏は、
武士でありながら、
桓武天皇と清和天皇という
天皇の権威を借りて、
自らを権威建てようとしました。
この桓武平氏と
清和源氏が
武士団の二大棟梁なのであります。

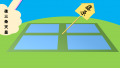




コメント